こんにちは、ちさとぱぱです。
このブログでは私の経験を基に住宅設計についてのいろはを記事にしています。

住宅設計ってどうやるんだろう?
何から始めたらいいかわからない。。。
基本的なことで先輩に聞きにくいな。。。
こんな悩みを持たれている方は実は多いと思います。
私自身、住宅設計は中途入社の会社で初めて担当しました。
その時に新卒でもないのに何でもかんでも先輩に聞くのは迷惑かな?
と思いインターネットで調べたり本を読んだりと苦しんだ思い出があります。
同じような思いをされている方の為になればと思い、
当時の事を思い出しながらこのブログを書いています。
住宅設計とは?

ご存知の通り、お家の間取りを考え、家を建てる為の図面を書くことです。
工事現場では設計の書いた図面を基に全てが進んでいくわけですから、
住宅が建つうえで最も重要な仕事といえるでしょう。
住宅設計のポイントは?
住宅設計をするうえで最も気を付けるべきポイントは、
設計の為の家ではなく住む人(施主)の為の家であるという事です。
自分の想いを実現したいがためにお施主様に無理を強いる建築家はよくいます。
無理を強いた結果、奇抜な住宅となりますので建築雑誌などでは大々的に取り扱われます。
例えば、見晴らしのいい高台で大きな窓を設けた住宅は,直射日光が入りすぎたり、
高台下の道から家の中が丸見えだったりという理由で実際にはカーテンを閉めっぱなし。
これではお施主様の為を考えた設計とは言えません。
実際に設計をする上では、お施主様のことを第一に考えなければいけません。
住宅設計に必要な「モノ」

大きく分けて2つの必要なものがあります。
・知識
・技術
どちらもしっかりと身に付けなければお施主さんに最善のご提案が出来ません。
必要な5つの「知識」
・寸法
間取りを書く上でこの知識が無いと書き始めることもできません。例えば椅子の高さや椅子から立ち上がる際に必要な寸法など、わからないまま出来上がったプランは生活しづらい可能性があります。
・土地
不動産屋さんに聞けばいい。と思うかもしれませんが、不動産屋さんは土地の金額や相場には詳しいですが、土地に関連する法律にはあまり詳しくありません。
・法律
土地に関連する法律も大事ですが、住宅設計をするうえでの知識ですので、家の中の法律もしっかりと身に付けましょう。かっこいいからと窓の少ないプランを書いて、契約後に採光・換気・排煙がクリアできませんでした。。。なんてかっこわるいですよね。。。
・お金
お金を払うのはお施主様ですので、提案する設計がお金のことをわかっていない場合に困るのはお施主様です。何にどれだけのお金がかかるのか大まかにでも把握しておかないと一度提案したものを覆さないといけなくなります。これもかっこわるいですよね。。。
・植物
これは私の場合なのですが、自分が植物が好きだからお施主様にも植物のお話をします。育てている植物や好きな植物をお伺いし、そこから好きな家の雰囲気を想像します。
これは植物に限らず、ご自身の好きなことでいいと思います。
バイクが好きなら関連して車についても詳しくなっておけば、そこからお施主様の好みが見えてくるかもしれません。
必要な2つの「技術」
・現場力
優れた間取りを作れたとしても、それが実際には建てられない。なんてことにならない為にも「現場力=納まりの理解度」が重要です。
一般的な納まりがわかっていれば、時にはイレギュラーな納め方も自分から工事監督に提案できるかもしれません。それがお施主様の為にも繋がってきます。
・想像力
前述の植物の話の様に、お施主様との会話から設計の糸口を見つけられるかもしれません。その糸口を見つける為には想像力を鍛える必要があります。
設計始める前に揃えておきたい「道具(モノ)」

設計には知識と技術が必要と書きましたが、この2つを身に付ける為に、
または仕事をするうえで必要な道具をご紹介します。
「道具」一覧
・メジャー(コンベックスやスケールとも言います)
・テープメジャー(スケールテープとも言います)
・バインダー
・パソコン
・三角スケール
・消せるボールペンと消せるマーカー
・電卓
・事例写真
道具の役割
・メジャー
打合せでも現場でも、どこでも何かを測ったり、お施主様に大きさを説明したりと大活躍です。
(私は車と鞄と事務所にそれぞれ1つずつ持っています。)
・テープメジャー
土地の調査の際に必要です。
・バインダー
土地の調査の際にあると便利です。
・パソコン
当たり前ですね。
・三角スケール
建築図面は様々な縮尺で書かれていますので、それぞれの図面から寸法を読み取る為に1つの物差しに6つの縮尺が割り振られた、設計なら絶対に持っている。そんな三種の神器的な道具ですね。
・消せるボールペンと消せるマーカー
所謂フリクションです。打合せの際には書いたり消したりまた書いたりまた消したり。お施主様との打合せで文字や線を消さないなんてことはあり得ません。絶対に必要です。最近はマーカーまで消せるので、私も愛用しています。
・電卓
スマホの電卓でもいいんですが、「MC/MR/M-/M+」などの機能がある方がいいですね。採光計算や換気計算、斜線計算など。設計業務にはたくさんの計算がついて回りますので。
・事例写真
お施主様にこちら側のイメージを伝えるうえでの最強手段です。
インターネットで画像を漁ってファイリングしたり、タブレットに保存しておくと打合せの際にとても便利です。
「知識」を身に付ける為に

住宅設計をするには「知識」がとても大切です。
正しい知識が無いとお施主様にご迷惑をおかけしてしまうからです。
しかし、「知識」があれば「センス」が無くてもよりおしゃれな設計が可能になりますので、その 観点からも私は「知識」が最も大切だと考えています。
その「知識」を身に付ける為の方法は様々ありますが、私が意識している5つをご紹介します。
街ぶら
「知識で街ぶらって。笑」
と思った方挙手!!
街ぶらをなめちゃいけません。
ただ街を散策するという意味ではなく、「街ぶらで観察力を磨く」という意味です。
当たり前ですが、街があれば建物があります。
この建物は誰かが設計した建物なのですから、街中の建物全てが設計事例なのです。
街中の設計事例を見るうえでのポイントは3つ
①全体を俯瞰してみる
②細部を注視してみる
③その他の関係性を見る
この3つのポイントを押えて見ることで、①建物の建っている場所にはどんな魅力がありどんな問題があるのか。②その魅力をどのようなアプローチで建物に反映し取り入れているのか。また、その問題点をどのようなアプローチで解消しているのか。③そのアプローチにより街と建物がどのように関係を持っているのか。
これらを日ごろから考えることを習慣化することで、常に「なぜ?」を持つことが出来るようになります。この「なぜ?」がお施主さんに対してのより良い提案へと繋がっていきます。
役所調査
街ぶらで見つけた「なぜ?」も役所調査により歌唱される場合もあります。
実際に設計をする際にはまず土地情報を入手することになるでしょう。
その入手した土地情報を基に現場に行き、どんな家を建てようか想像すると思います。
ただし、どんな土地にも法律による制限が掛かります。
この制限がどのような内容なのかを調べることを役所調査といいます。
まずは今受け持っている物件の土地資料と公図、謄本を取得して役所に行ってみてください。
具体的には建築指導課にて
「この土地に家を建てたいんですけど、何もわからないんでおしえてください~」と、
下手に出ればお役所の方は丁寧に教えてくれます。(たまに不親切な方もいますが。。。)
そして、その際には下記の資料を持っていくと調べやすいと思います。
これは私が実際に使っている資料で、この内容に沿って土地の現地調査と役所調査をすれば、土地に関するほとんどの情報を調べ上げられると思います。
調べていく中でわからにことがあればその都度調べることで徐々に法律に関する知識も深まります。
ホームセンターに行く
お金に関する知識を収集するうえで、製品の金額は業者さんに聞けばいいですし、ローンの事は銀行の方に聞けば十分です。
しかし、造作(作り付けの家具など)をご提案する際にどのくらいのお金がかかるのか。
これを理解するには、自分の提案するものをホームセンターにあるもので作るといくらかかるのかを調べるという事が、金額についての知識を自分に落とし込みやすい方法だと思います。
ここで算出した金額に大工さんの手間代を含め、会社の利益を載せたものがお施主様に提示する金額と考えてください。
この金額を自分がどう感じるか。高いと思うのか、安いと思うのか。
高いと思うのならどうすれば安くなるのか。
ホームセンターにある材料で代替品となるものがあるかを探すという事も、お施主様に対してのよりよいご提案につながると思います。
事例研究
ここまでは自分で課題を見つけて調べるという内容でしたが、
この「事例研究」が知識を深めるうえで一番大切なことです。
方法としては、お勤めの会社の施工事例を完成車芯から施工図、確認申請図面まで事細かに読み漁る。というものです。
ただ眺めるのではなく、「読む」という事が大切です。
特に確認申請図面には設計に関係ないであろう文章が多く書かれている場合があります。そのほとんどが法律に対しての回答となる文章ですので、それがどういう法律なのかを調べるようにしましょう。
また、施工図ではなぜこの部分の詳細図が書いてあるのか。などを理解することによって、美しく見せる為の納まりを学ぶことが出来ます。
そして、読み漁る際には最低5つの「なぜ?」を見つけるように気を付けることでご自身のレベルアップに繋げられますので、チャレンジしてみてください。
植物
なんでもいいんです。
ご自身の好きなことで、お施主様との会話の種になりそうなことを深堀してみてください。
その深堀した知識が、ある日役に立つことがあります。
間取り作成の突破口になる場合があります。
仕事の事だけでなくご自身の趣味を突き詰めることも住宅設計の「タメ」になる事がありますので、
仕事以外も全力で取り組んでください。
「技術」を身に付ける為に

設計に技術。というとCADの技術くらいしか内容に思われるかもしれませんが、
出来る建築士は現場での技術も持っているものです。
現場を知っているから設計に反映させられることも多くあります。
工事監督とおでかけ
現場での技術を身に付ける為には工事監督とのお出かけが一番の近道です。
地縄を貼りに行ったり、上棟の際の気密テープ施工を手伝ったり、配筋検査や金物検査に同行して、工事監督にウザがられながら質問攻めにしたり。
現場を知ることで、どのように作るのか、図面に書いているこれはこういう風に出来るのか。など理解することが出来ます。
キッチン前の腰壁笠木をどうやってついているのかを知れば、腰壁に付けるコンセントの高さや付け方を細かく検討することが出来ます。
図面上では納まるのに現場では納まらない。
なんてことはしょっちゅうあります。
そのしょっちゅうある状況を可能な限り発生させない為にも現場を知るということは大切な技術です。
妄想する
「妄想力」=「想像力」=「創造力」
間取りを書く際にはお施主様からのヒアリングを行います。このヒアリングの際に聞いた内容を基にお施主様がどのような生活をするのかを妄想することが間取りを作るうえで大切だと思います。
例えばコーヒーが好きなご夫婦で、毎朝コーヒーを飲まれるのであれば、ダイニングテーブルには朝日を取り入れてあげよう。とか、おっとりした雰囲気の奥様の為に家事導線の中心に少し腰掛けられる家事スペースを作っておけば、毎日の家事の中でふとした瞬間に座って落ち着く生活を提供できます。
また、リビングから続くウッドデッキが欲しいのであれば、その方が広いと感じるのは縦ではなく横なのかもしれません。それなら吹抜を作るよりも地窓などで外の空間を室内に取り込むご提案の方が喜ばれるかもしれません。
間取りを作るうえで妄想することはお施主様の暮らしを想像することであり、その想像を現実の物へと創造していくことが住宅設計の大切なお仕事です。
まとめ
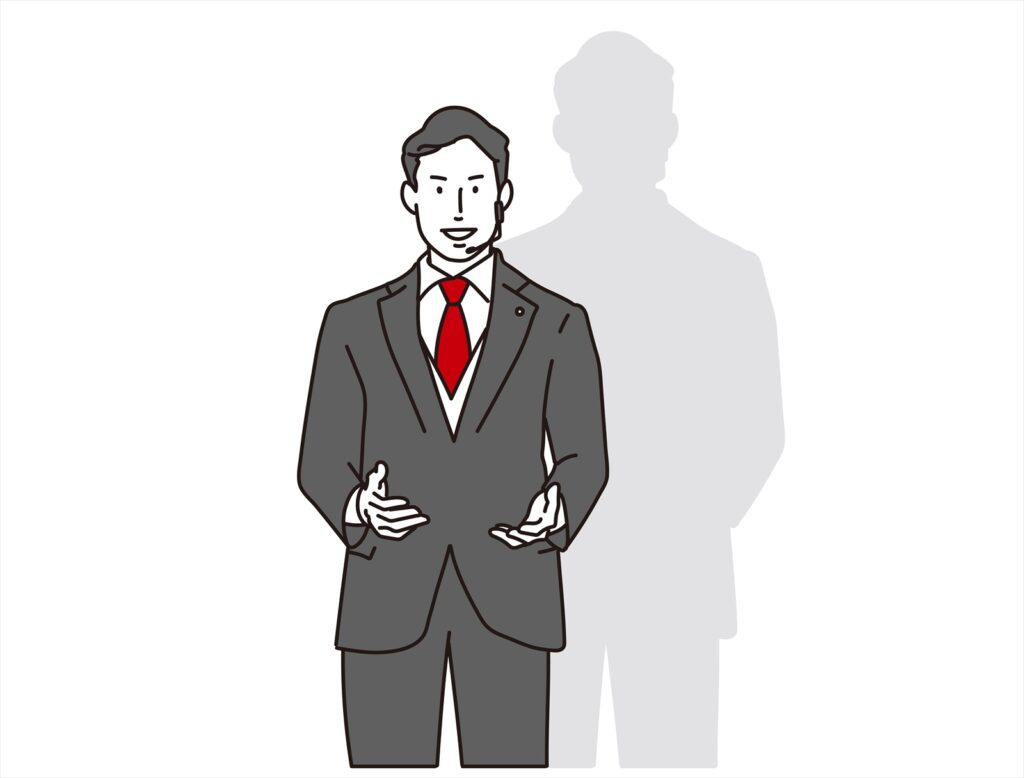
ここまで住宅設計において必要となる3つの「モノ」について書いてきました。
お施主様へより良いご提案をするには設計をする側の正しく幅広い知識が重要だという事をわかっていただけたのではないでしょうか?
この「正しく幅広い知識」は一朝一夕に身につくものではありません。
ただ、私のこのブログを最後まで読んでいただけたという事は、より良い設計をしたいという想いを持った設計さんだと思います。
これからも様々な知識を身に付ける為の情報収集を心掛けて、より良い設計をして頂けるとブログを書いた身としても幸いです。
私自身が住宅設計を始める際に読んだ書籍のリンクを下記に貼っておりますので、より深く住宅設計の為の知識を身に付けたい!という方は是非読んでみてください。
最後まで読んでいただき本当にありがとうございました。



コメント