こんにちは、ちさとぱぱです。
このブログでは私の経験を基に住宅設計についてのいろはを記事にしています。
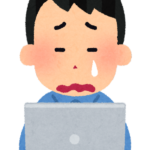
プランを描く前に土地を見てこい。って言われたけど何を見ればいいのかわからない。。。
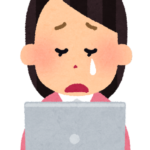
これから家を建てる土地、営業さんに任せっぱなしで良いのかな?
こんなお悩みを抱えているあなた!
一級建築士としてこれまで100件の住宅設計に携わってきた
「ちさとぱぱ」が建築予定の敷地で見るべきポイントと調べるべき内容をお伝えします!!
まずは!
敷地調査とは

図面を描くためには設計条件の整理がとても大切です。
その中でも特に重要となるのが敷地条件です。
この土地に家を建てる為にはどのような条件をクリアする必要があるのか。
この敷地条件の確認についてよくあるNG行動が「不動産屋に聞く」です。
ベテラン営業マンでも売ってる人が言ってるんだから大丈夫。
とか、土地の売買契約でもらう資料に書いてあるから間違いない。
とか、そんなことを言う方は結構いますが、「NG」です。
あくまで不動産屋さんは土地を売るのが仕事ですので、
そこで家を建てる為の条件まで細かく調べてはいません。
自分の目で見て足で動いて敷地条件は調べるようにしましょう。
敷地調査の進め方
さて、調査の進め方ですが、大きく分けて3ステップです。
Ⅰ.事前調査
Ⅱ.現地調査
Ⅲ.役所調査
この3ステップで敷地の全容が見えてきます。
Ⅰ.事前調査

敷地調査の基本は現地に行って、役所に行って。というのが当たり前でしたが、
最近はインターネットで8割の調査は完了します。
GoogleMapで確認して、行政のホームページで確認して、便利なサイトを活用して。
これで基本的なことはわかってしまいます。
①GoogleMap
まずはGoogleMapで調査です。
1.敷地の方位
不動産資料などでも確認できますが、磁北で記載されることも多い為、
GoogleMapで真北を確認しましょう。(国土地理院の地図が一番正確です。)
2.交通事情
道路の幅や曲がり具合、工事車両のアクセス方向や、迂回路などの確認をします。
3.周辺施設の確認
最寄り駅やコンビニ、公共施設、公園の位置とそこまでの最短ルートを確認します。
この際、周辺に水に関わる地名が無いかも確認しておきましょう。
4.航空写真モードで確認
周辺の建物や駐車場の配置、屋根の形状、緑の分布状況等を確認し、
見通しの良い方向や借景出来る要素の目途を立てておきます。
(現地で確認は必要です。)
5.ストリートビューモードで確認
ストリートビューでは周りの建物の高さや電柱、道路幅員、歩道や擁壁の有無、
見通しの良い方向、隣家の窓位置などを確認できます。
また、既に解体済みの古屋が移れば年代を推測して水道の引き込み管が古くて使えないことにも気づくかもしれません。
②インフラ調査
続いてインフラについてもインターネットや電話で調べることが可能です。
1.下水
下水については多くの市町村で下水道台帳を公開しています。前面本管の大きさや引き込み管の大きさなどもわかります。
また、雨水と汚水が分かれているのか、合流なのかもわかるようになっています。
http://www2.wagamachi-guide.com/hiroshimacity/
ある程度大きな市であればこのようなサイトがありますので調査が可能です。
2.ガス
地域によってはガス本管の埋設状況もガス会社のホームページで調べることが可能ですが、基本はガス会社に電話して住所を伝えて調べてもらう。というのが一般的です。
プロパンガスをおいている家が無いから都市ガスだろう。と思っていたら
集中プロパンの地域でガス代が想定よりも高かった。
なんてことにならない様に事前に調べておきましょう。
③地盤調査
地盤も可能なら調べておいて損はありません。
お客様に事前に地盤補強の費用がかかるリスクについて説明が出来るからです。
私が一番お勧めしているのが「地盤ネット」です。
https://jibannet.co.jp/karte/
住所を入力して1分で地盤カルテを作れますので、お客様への説明資料にも使えます。
④都市計画について
都市計画もインターネットでほとんどが調べられます。
http://www2.wagamachi-guide.com/hiroshimacity/
この様なサイトを見ながら、下記のエクセルシートを埋めていってみてください。
埋まらなかった箇所は現地調査が必要です。
https://ichito.tao-archi.com/wp-content/uploads/2023/04/敷地調査報告書原本0409.xlsx
Ⅱ.現地調査

さていよいよ現地調査です。
現地調査ではあらゆるものの「高さ」を確認することが大事になります。
では行きましょう!
①写真撮影
現地調査における最大の目的は設計の「手がかり」を発見することです。
ストリートビューで概要は把握できますが、現地へ行ってみて初めてわかることもたくさんあります。
現地では設計や工事の視点で寸法を測りながら詳細に観察することでその土地の特徴を発見できるはずです。
では写真は何を照れば良いのか。
まずは敷地の中心に立ってぐるりとパノラマ写真を取りましょう。
続いて境界杭や電柱、電線、借景出来そうな隣家の庭、擁壁や桝、メーターなども取っておくと良いでしょう。
目に映るもの全てを写真に収めておくことで、後日状況を確認することが出来ます。
②高さの確認
「高さについての情報」は現地を見ないとなかなかわかりません。
そして現地調査の5割は高さの確認だと思ってください。
最初に敷地と道路、敷地と隣地の高低差を測定し、高低差がある場合は段差の処理方法を確認します。
この処理方法が擁壁なのかCB・CPなのか、間知石なのかも確認してください。
道路と敷地の高低差ではこの高低差をどう処理するかを考えましょう。
高低差が40cmを超える場合は深基礎やL型擁壁等も含めて検討します。
40cm以下であれば100mm厚の補強CBで処理が可能ですが、それ以上の場合は150mm厚以上の型枠CPでの処理が必要となります。
1m以上の高低差となる場合は審査機関と事前に相談しておくと良いでしょう。
③擁壁の確認
境界に沿って擁壁がある場合はその高さを計測します。
L型擁壁であれば安心ですが、明らかに古くて2mを超える擁壁がある場合は要注意です。
崖条例等の規制がかかる場合があります。
また、間知石の場合はその上に積めるCBは2段までです。
それと、ブロック擁壁も原則2段までしか積むことは出来ませんので、
土圧のかかるブロックが3段以上ある場合は土の処分費がかかることを想定します。
④敷地境界関係
境界鋲や境界杭の有無を確認し、無い場合は境界確定の必要があるかを確認します。
既存ブロックなどで境界線がある程度わかるようであればお客様判断でも良いですが、
境界の目印となるものが無い場合は原則境界確定をした方が良いでしょう。
また、敷地境界線に沿って積まれているブロック塀にも注意が必要です。
ブロック塀の高さが1.2m(6段)を超えている場合はブロック塀の高さを低くする必要があります。
(控え壁を設置することで安全性を確保できる場合もあります。)
https://www.mlit.go.jp/common/001239762.pdf
https://www.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/4983.pdf
詳細の規定は上記の2つの資料を確認してください。
⑤工事車両の出入り経路
工事車両が入れないと資材の小運搬費用や手起こしの費用等がかかってしまいます。
工事車両は最低でも4tトラックがは入れるかを確認しておきましょう。
注意すべき点は
クランクしている箇所、電柱、物置、自動販売機などです。
⑤桝やメーターの位置
敷地内にある既存引き込みを活用できれば建築費用を抑えられます。
建物の配置計画や設備図面を書く際にも必要となりますので、位置を計測し図面に書き込んでおきましょう。
⑥日当たりや抜け
敷地ではメリットとなるものを探してください。
隣家の樹木やオープンスペース、抜けのある方向などに注目します。
これらを意識しながら設計すれば密集地でも豊な空間を提案することが可能です。
最近はスマホアプリで現地の日照(太陽の軌道)を確認できるものが多くありますので活用してみてください。
また、メリットと反対にデメリットも探します。
例えば隣家の窓です。窓と窓が向かい合ってしまうとカーテンも開けられなくなりますので注意しましょう。
Ⅲ.役所調査

役所調査では「法律」について調べます。
どんな土地でも法律による規制があります。
一般的な建蔽率や容積率のほかにも、地区計画や宅造規制、防火規制などなど。
知っておかないと申請を出した後でお客様にお詫びすることになりますので注意してください。
そして役所調査で一番大事なことは「素人になりきる」です。
本当に法知識が豊富な方は別にそんなことしなくてもいいんですが、
まだ慣れていない方は「ぼく何もわからないんです~。」
というスタンスで役所調査は行いましょう。
役所の人は基本的に親切なので、めんどくさがりながらもきちんと教えてくれます。
①事前調査の再確認
まずは事前調査で調べた内容に間違いが無いかを関係課で確認します。
これが間違えていると前提から崩れますので、めんどくさがらずにやりましょう。
②確認申請前に必要な手続きについて
確認申請前に手続きや協議が必要な内容を調べます。
2項道路や地区計画、宅造法、風致地区、土地区画整理法や計画道路など
たくさんの種類があり、それぞれ担当課が違います。
手続き自体はほとんどが図面数枚と申請書1枚程度で済むものですが、
この手続きを怠ると確認申請の許可が月単位で遅れてしまいますので注意してください。
また、内容についてはパンフレットなどがありますので必ず入手するようにしましょう。
③道路関係
「幅員4m以上の道路に2m以上接している」という「接道」
これは基本であり最も重要な建築基準法のルールです。
しかし、敷地の前に4m以上の道があってもそれが「道路」ではない場合もあります。
なので道路管理課などで前面道路の「道路種別」は必ず調べるようにしましょう。
これを怠ると、基準法43条の申請を見落として、準防火仕様にする費用を
後出しでお客様に説明するという地獄を見ることもあります。。。
④周辺建物の概要書を入手
建築指導課では確認申請の際に提出する概要書を閲覧することが出来ます。
これを見ることでその土地で建築する際に関連する法律を知ることもできます。
特に配置図と概要書第二面の内容は網羅するようにしてください。
地域によってはコピーをくれるところもあるので聞いてみてください。
まとめ
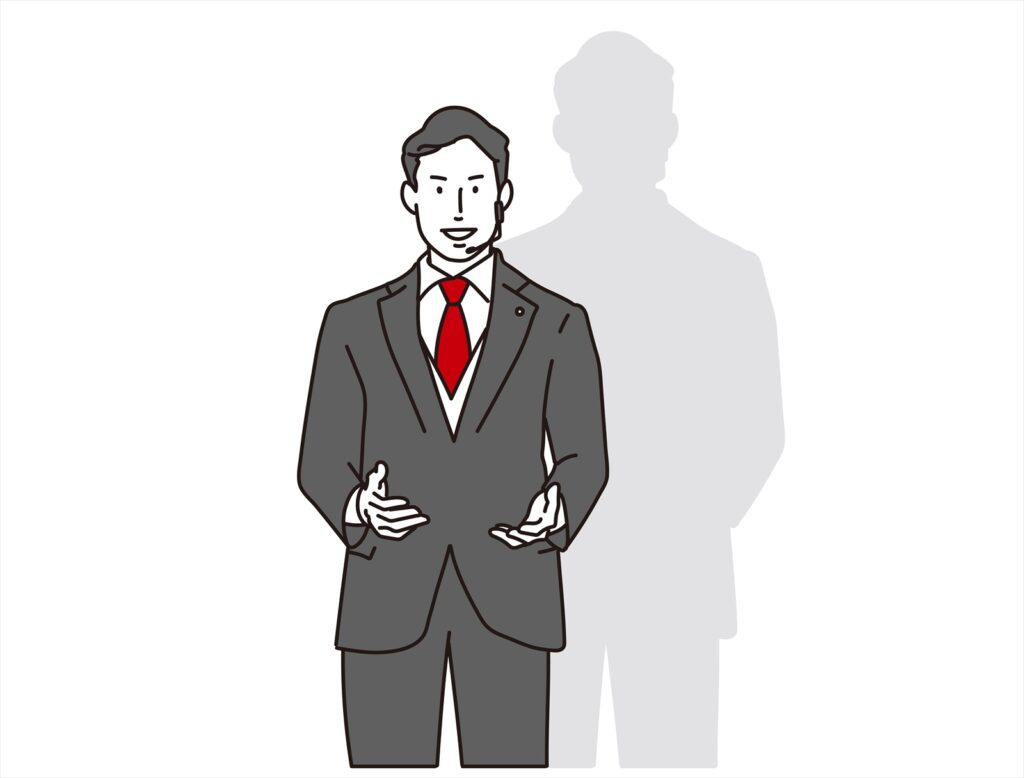
いかがだったでしょうか?
設計する前の敷地調査でもやるべきことがたくさんあります。
最初の内は「あれを調べてなかった!」などの失敗もあると思います。
ですが、何件かやってみてください。
自然と法律の事も頭に入っていき、お客様にも説明が出来るようになります。
設計事務所ではこの調査は当たり前に行いますが、
ハウスメーカーではここまで調べたことが無いという方も多いです。
この記事を読んで頂き実践した方は他の設計や営業よりも一歩先の知識を手に入れることが出来ます。
繰り返し読んでいただき、実践してくださることを願っています。
最後に大切な3つのポイント
・敷地調査は事前調査が8割
・現地調査では5割が「高さ」の調査
・役所調査では「素人」を演じる
ただ、法律関係は難しいこともたくさんあります。
以下の書籍は私が読んで参考になったもので、いつも机のすぐ手が届くところに置いてあります。
ぜひ参考にしてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。




コメント